最小二乗法の復習
個のデータ
が与えられています。
で、
と表します。
線形回帰モデルは以下のよう表されるとします。
ただし、です。
また、を以下のようにおきます。
この時、目的関数を以下のように定義します。
目的関数を最小化したを
と表すと
となります。
最小二乗解の幾何学的解釈
を以下のようにおきます。
(1)と(4)をまとめて書きます。
(4)を(6)に代入します。
ここで、を
の
番目の列ベクトルとします。
の部分空間
は
で張られています。
PRML演習問題 3.2(標準) より、を部分空間
へ直交射影したものが
ということになります。
に対する最小二乗解は、部分空間
内にあり
に最も近い
を選ぶことに相当します。
イメージ図を以下に記します。

偉人の名言
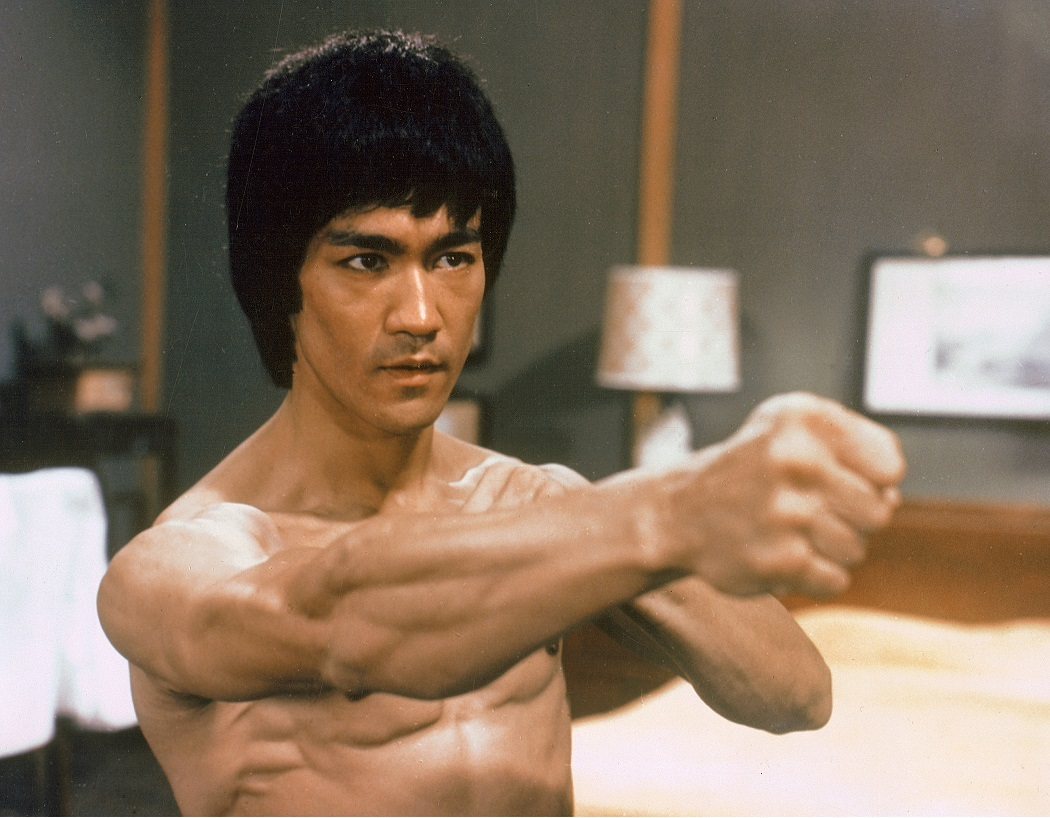
目標は必ずしも達成されるためにあるのではない。
目指すべき何かを与えてくれることも多い。
ブルース・リー